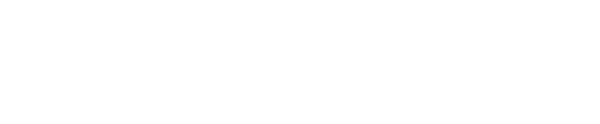リズム感を鍛えたい!
リズム感を鍛えたいと考えたとき、オススメしたい方法はいくつかあります。
先に答えを言ってしまえば
ポイントは三つで
- 楽器に触れてみましょう
- リズム感の良い曲を聴こう
- リズムの裏を知りましょう
ということになります。
詳しい解説の前に、よく言われている話ですが
「なぜ日本人のリズム感が世界と比べて遅れているのか?」
ということの理由について考察してみたいと思います。
日本人と海外の人、リズム感の決定的な違い
これはそもそもの音楽の発祥や好みの違いからくるものです。
国ごとでの音楽を考えてみましょう!
日本の音楽
例えば雅楽や童謡などを聴いてみると、一音一音をかみしめて「いかに美しいメロディーと歌詞を付けられるか」で表現しているように思います。
童謡「さくらさくら」の冒頭は
「さ~く~ら~、さ~く~ら~」
音がをずらしたりせず、すべて拍の頭に音が始まります。
「さっ、くらっ~」「さーくっら~」みたいには歌わないですよね(笑
日本で重要視していたものは美しさ、優雅さだったんです。
君が代でも考えてみましょう。
「きーみーがーあーよーおーはー」
すべて拍の頭にスタートがあり、美しい展開をしてく構成です。
これが国歌ですから、かっこよさやグルーブ感というものを優先せず美しさを追求したことが分かりますね。
海外の音楽
アメリカなんかではブラックミュージックやラップ、R&Bなど、日本とは対照的にグルーヴ感ありきのジャンルが多く生まれています。
喜びも悲しみも娯楽でさえ、音楽を通してさまざまな感情を表現しようとしてきた歴史があります。
楽しい気分を表現したりダンスに合う曲を生み出すには、歯切れの良い16分音符や32分音符が必要だったのかもしれません。
こうした背景や歴史があり、双方が重視していたものに特化した音楽が完成しました。
近年では日本の音楽も世界のリズム感やテクニックを吸収して、さらに多種多様で魅力的な音楽も完成するようになりました。
そのような名曲を完成させるために、作り手や歌い手が様々なジャンルのリズムを体で覚えていくことはとても大きな武器になります。
ここからは具体的にどうしたらリズム感を養っていくことができるのか、解説していきたいと思います。
リズム感を鍛える方法
楽器に触れてみましょう
まずは一番効果が実感できるこちらの方法「楽器」です。
自分が興味のある楽器なら何でも良いのですが、
- エレキ
- ベース
- アコギ
- ピアノ
- シンセサイザー
- ドラム
- カホン
- ほか弦楽器や管楽器
たくさんある楽器の中に興味のある楽器はありますか?
楽器を触ることで、自然とリズム感は向上していきます。
「とにかくリズム感を鍛えたい」という方には
打楽器系がベストです。
単純に音数が必要で、リズムに特化した楽器だからです。
「弾き語りがしたい」という人でしたらアコギですね!
最初はジャラーンと1回弾いてみるだけでも、歌いながら弾くことの難しさが感じられると思います。
しかしある程度なれてきたら、リズム感が付いてきた証拠です。
弦楽器は知らないうちにリズム感が鍛えられているのでオススメですよ。
「ピアノが好きだったりDTMもやってみたい人」なら、ピアノやシンセサイザーも触ってみると良いかもしれませんね。
鍵盤楽器は一番いい音が出しやすい分、一番形になりやすいと思います。
こちらも知らないうちにリズム感が鍛えられて、弾ける音数もどんどん増えていくはずです。
リズム感の良い曲を聴こう
次の方法は「リズム・グルーブに優れた曲にたくさん触れましょう」という内容です。
日本人が日本語がペラペラなのは、勉強をたくさんしたからだけでなく「生まれた頃から触れている」からです。
留学した人が、人より英語が上手になるのは常に触れていて使わざるを得ないからだそうです!
よく「作曲する人は洋楽を聴くと勉強になる」という旨を見聞きしますが、あながち間違いではない気がします。
日本にはないコード展開やリズム感を体に染みこませることは、新しい発想や展開を広げるのにもってこいだと思います。
リズムの裏を知りましょう
そして最後は少し応用編です。
普段聞いたり歌ったりする曲の裏を感じるクセを持ちましょう。
どんな曲でも倍! 裏拍を感じるのはとても有効に働きます。
「さくらさくら」で考えてみましょう。
楽譜にするならこのようになります。
|○・○・|○・・・| ○・○・|○・・・|
|さーくー|らーーー|さーくー|らーーー|
普通感じているのは「○」の部分のみですが、その裏拍や休符などの「・」の部分も歌っているように感じてみてください。
適当に歌いながら体を動かしてみると、いつもより忙しく小刻みになると思います。
まとめ
今回はリズム感についての解説になりました。
「日本人と海外の重要視しているもの」そして「実際にリズム感を鍛えるための3つの方法」について書かせていただきました。
日本の音楽の美しさ、海外の音楽のかっこよさ、どちらもその文化を表した素晴らしいものだと思います。
みなさまが作り手・演奏者としてよりステップアップできますよう願っています。
いつも読んでくださりありがとうございます!